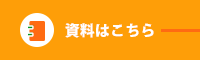日本の漢字の読み方
日本語には、「漢字」「ひらがな」「カタカナ」の三種類の文字がありますが、この中で最初に使われ始めたのは「漢字」で、中国から伝わり4世紀末頃から日本で使われ始めました。それまで日本の人々は口頭のみで様々なことを伝えていて、固有の文字を持っていませんでした。
日本での漢字の読み方は二種類あります。
一つは「音読み」といって、漢字と一緒に入ってきた中国での発音をもとにつけられたものです。例えば「山」という漢字の中国での読み方は「shān」なので、それがもとになって「さん」という音読みができました。
もう一つは「訓読み」といって、日本でもともと口頭で使われていた言葉を、同じ意味の漢字にあてはめていた読み方です。日本ではもともと山のことを「yama」と呼んでいたので、中国から入ってきた「山」という同じ意味の漢字に「やま」という「訓読み」をつけました。他にも、「紙」「水」「夜」の例を挙げます。
また、日本語の漢字には複数の「音読み」がある場合があります。それは、中国で時代や地域によって異なっていく読み方を、日本では追加していったからです。また、一つの漢字に複数の意味がある場合は「訓読み」も複数になります。日本語で最も読み方の多い漢字は「生」だといわれていて、外国人だけではなく、日本人でも読み方に迷ってしまうことがあります。
日本での漢字の読み方は二種類あります。
一つは「音読み」といって、漢字と一緒に入ってきた中国での発音をもとにつけられたものです。例えば「山」という漢字の中国での読み方は「shān」なので、それがもとになって「さん」という音読みができました。
もう一つは「訓読み」といって、日本でもともと口頭で使われていた言葉を、同じ意味の漢字にあてはめていた読み方です。日本ではもともと山のことを「yama」と呼んでいたので、中国から入ってきた「山」という同じ意味の漢字に「やま」という「訓読み」をつけました。他にも、「紙」「水」「夜」の例を挙げます。
また、日本語の漢字には複数の「音読み」がある場合があります。それは、中国で時代や地域によって異なっていく読み方を、日本では追加していったからです。また、一つの漢字に複数の意味がある場合は「訓読み」も複数になります。日本語で最も読み方の多い漢字は「生」だといわれていて、外国人だけではなく、日本人でも読み方に迷ってしまうことがあります。
_1.jpg)
_2.jpg)